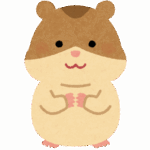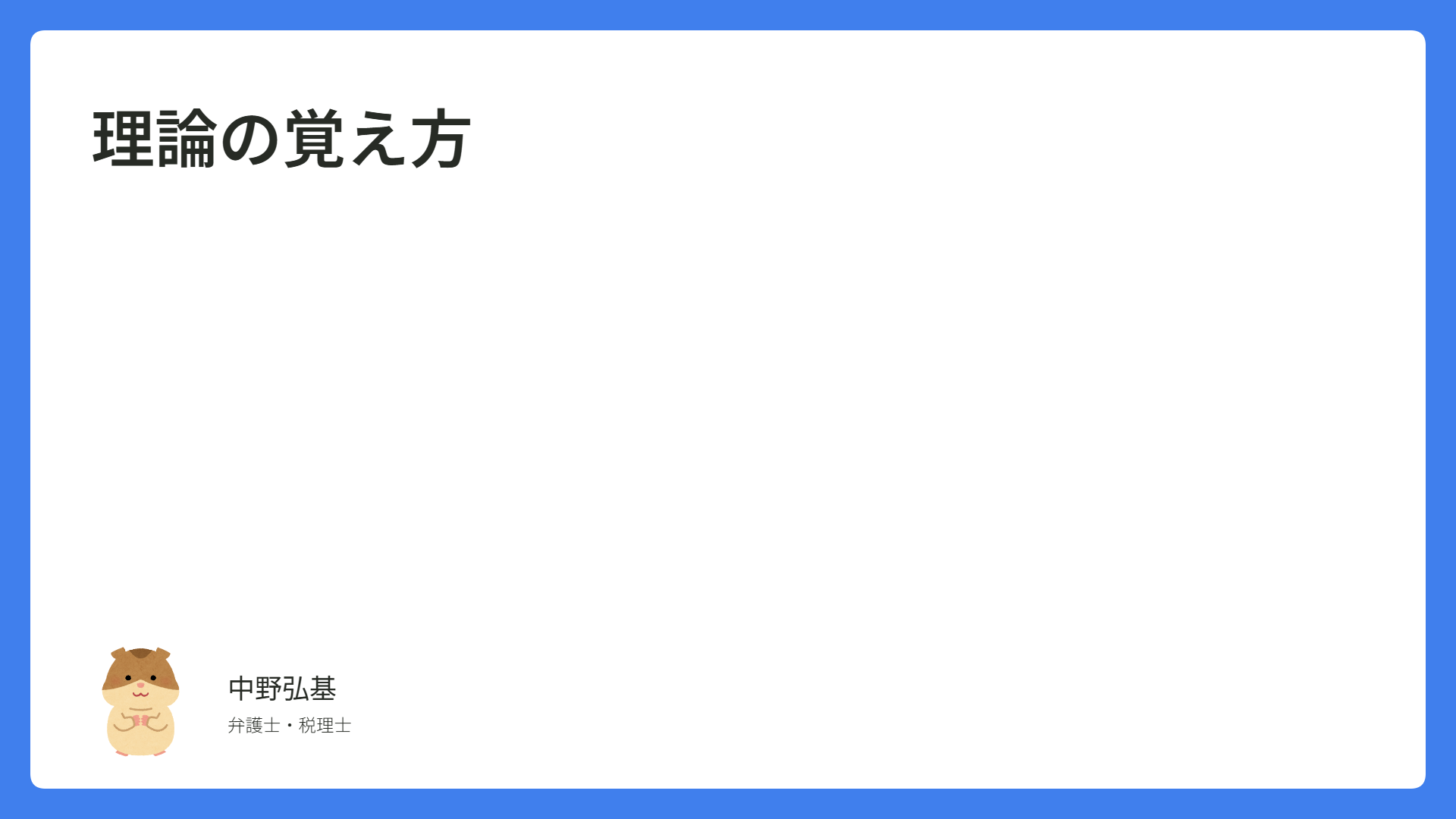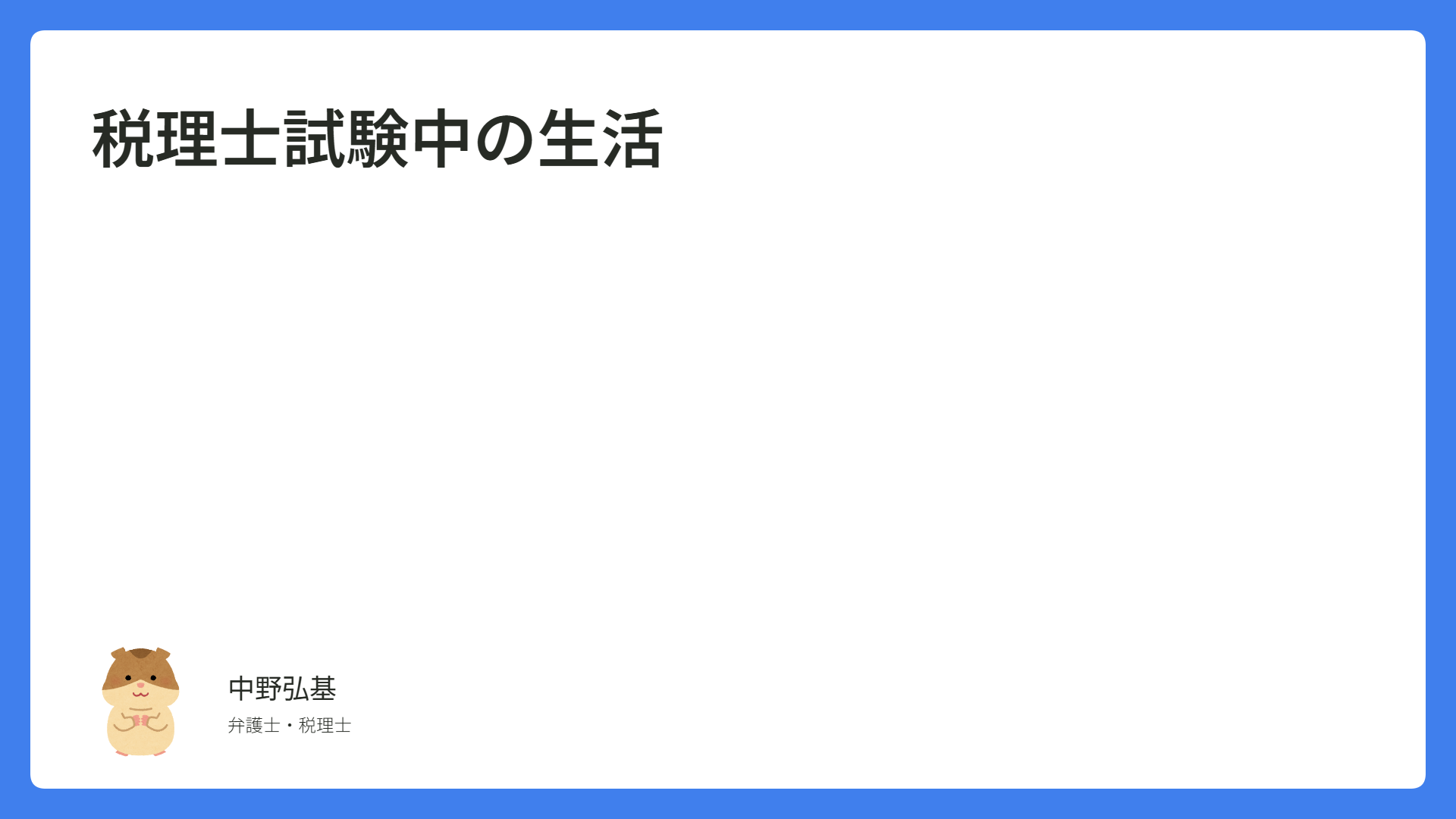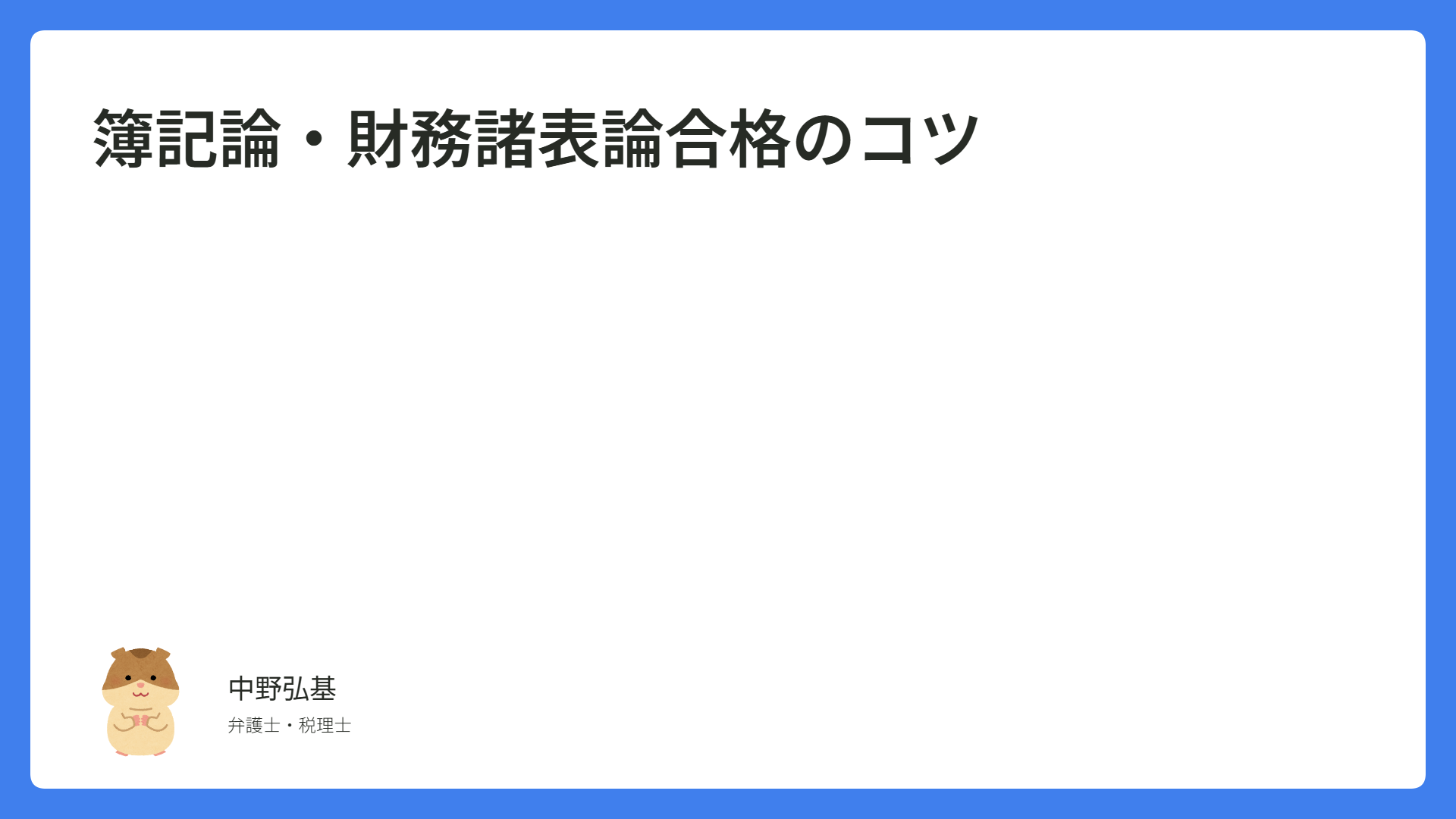消費税合格のコツ
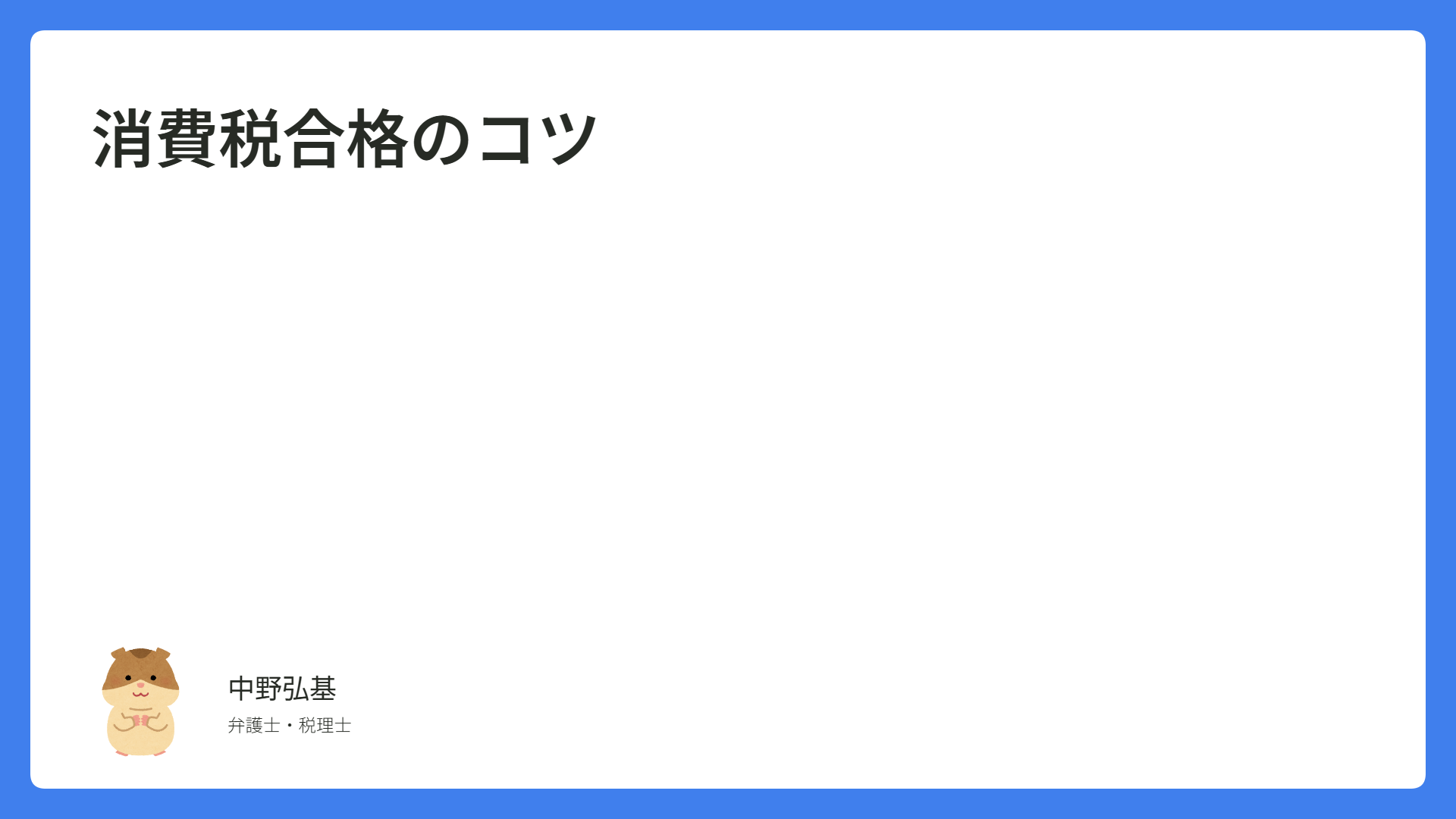

消費税合格のコツを教えて?

予備校以外のテキストや問題集に手を出さないことだよ

(どういうこと?)
消費税法の試験範囲は広くない
相対的な視点で考えると、消費税法の試験範囲は所得税法や相続税法よりも狭いと言えます。もっと狭い試験科目ももちろんありますが、所得税法や法人税法に合格してきた猛者にとっては、消費税法の試験範囲はそれほど広くないのです。
なので、消費税法を、所得税法や法人税法と同じ感覚で勉強していると、あっという間にテキストの学習が終わります。
実のところ、時間が余る、ということが、私を苦しめました。
私の失敗談
私は、大原のカリキュラムにしたがって、9月スタートで学習を開始しました。年内には基礎編が終わるカリキュラムでした。他の税法科目は週2コマの授業でしたが、消費税法は週1コマでした。
正直いって余裕がありました。
余裕があった結果、試験をなめてしまったのです。
遊んで勉強しなかったというわけではありません。
時間に余裕があったので、実務本に手を出して、あらゆる取引についての課税区分を勉強するようになったのです。英単語帳を勉強しているような感覚でした。
しかし、実務における消費税法は闇が深いです。(会計事務所にお勤めの方であれば、激しく同意していただけると思います。)あらゆる取引の課税区分をすべて間違えないようにするなんて、無理な話でした。
消費税法では、課税区分の処理の正確性のみが問われるわけではなく、消費税法全体の理解が問われます。課税区分の勉強に時間を食った結果、消費税法全体に対する勉強がおろそかになったのです。
基本的な課税区分を間違えるようでは勝負になりませんが、テキストに収録されるような課税区分ができるようになれば、そこから先の課税区分の知識では差が付きません。
我ながら、非効率な勉強であったと思います。
大切なこと
私の経験を踏まえてアドバイスするなら、予備校のテキストを信じましょう。予備校のテキストが完璧になるように勉強しましょう。予備校のテキスト以上の勉強をする必要はないです、ということです。
変に実務っぽいことを勉強する必要はありません。他の税法の学習でも、予備校の講師から同じことを言われると思いますが、消費税法は時間に余裕があるので、つい余計なことをやりたくなってしまいました。
ただし、試験範囲が広くない以上、テキストに収録されている内容に関しては、受験生は相当のレベルに仕上げてきます。計算は間違えないですし、理論も勉強しきってきます。
他の受験生に先んじるためには、予備校で学習した範囲については、誰よりも詳しく理解してください。
理論問題集の重要性は高い
消費税法の理論の出題は、いわゆるベタ書きではなく、事例問題の比重が高くなります。
なので、予備校で配布される理論問題集も理論テキストの一部だと思って、しっかり出力できるように仕上げていきましょう。
相続税法と同じ感覚で、ベタ書きの練習ばかりしていくと、他の受験生に競り負けます。
予備校の配布する理論問題集の模範解答が、本番でどう評価されているのかよくわかりません。
ぶっちゃけ、弁護士目線でいえば、法的3段論法は守っていないですし、一部の回答は日本語が破綻しているのでは?と思うこともありました。
とはいっても、受験生の大半が予備校の発行する理論問題集をまねて書いてくるので、予備校の回答には変に自己流で手を加えない方がよいと思います。
そういうものだと割り切って、文句を言わずに、理論問題集の言葉遣いを学習していきましょう。
まとめ
消費税法の試験範囲は狭いので、受験生のレベルが高い中で相対的に優位に立つ必要があります。
他の受験生より相対的優位に立つためには、実務本に手を出すのではなく、予備校のテキストが完璧になるように仕上げましょう。
もし本当に余裕があるのなら、実務本で勉強するのではなく、他の予備校が発行する問題集や模試を購入して解きましょう。
私も、大原に加えて、TACの市販の問題集や模試を解きました。
消費税法ほど実務で役立つ税法科目もないと思いますが、あえて実務と試験は割り切って、試験の勉強をしましょう。