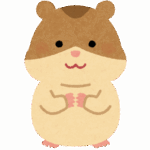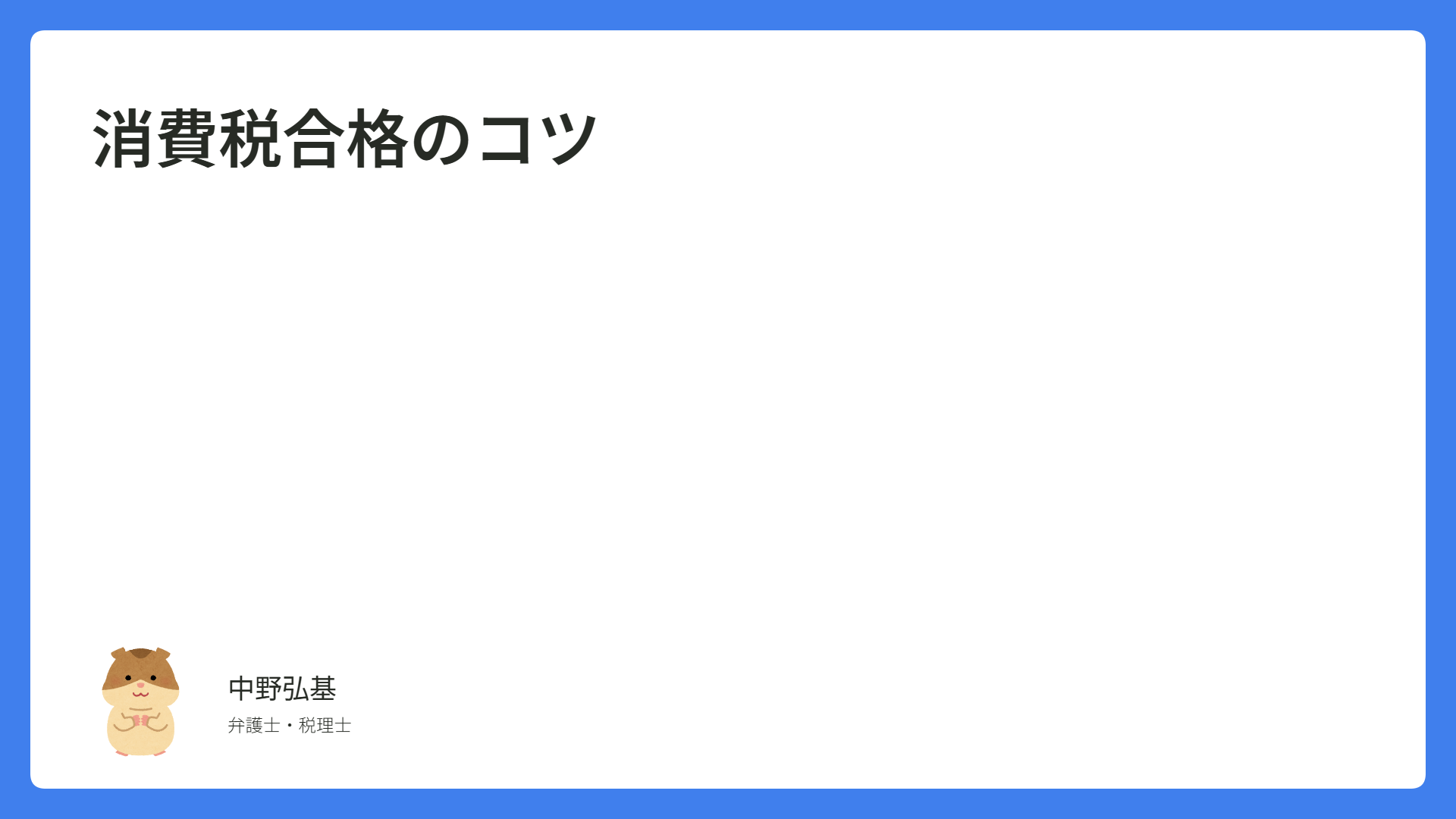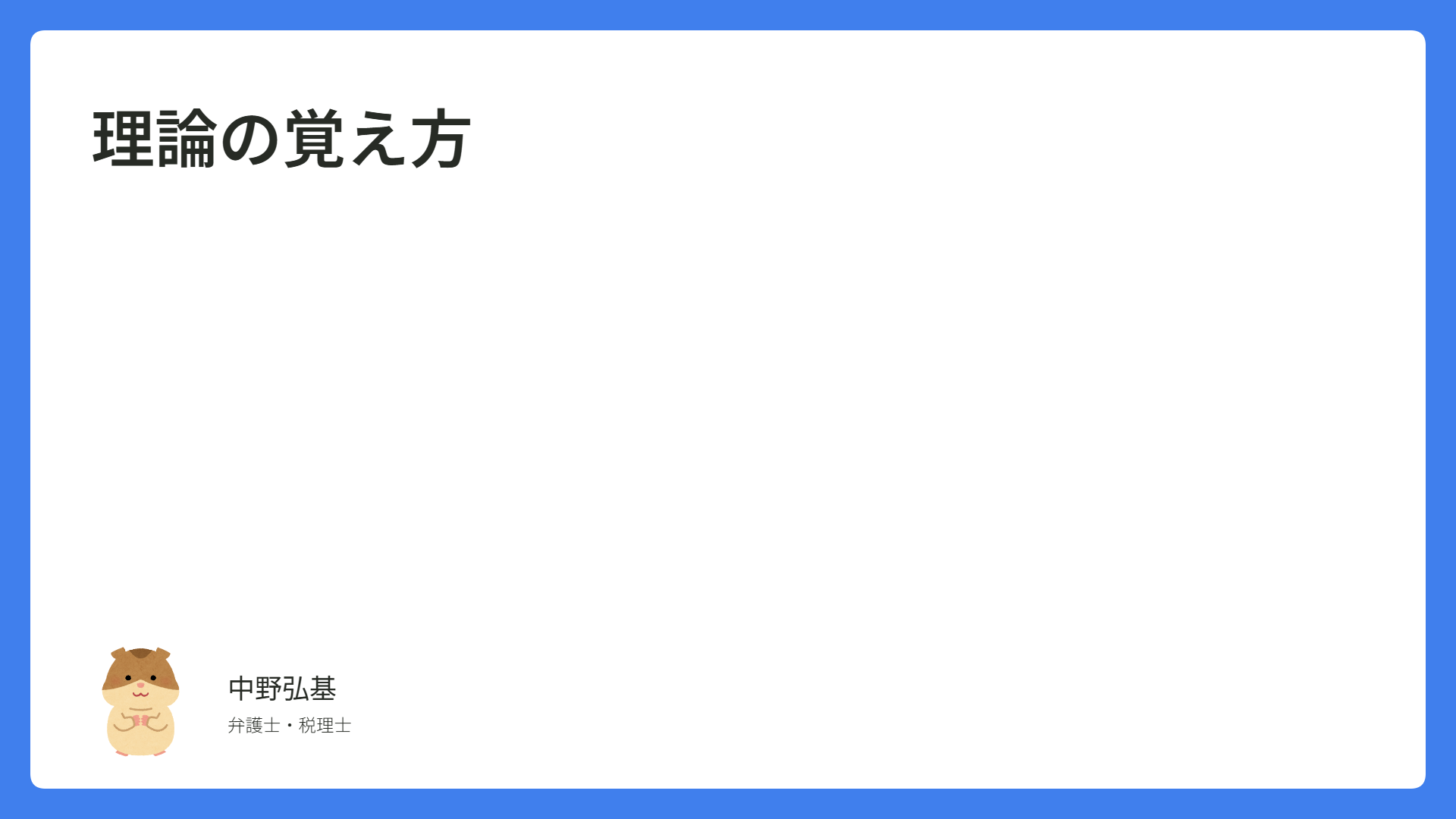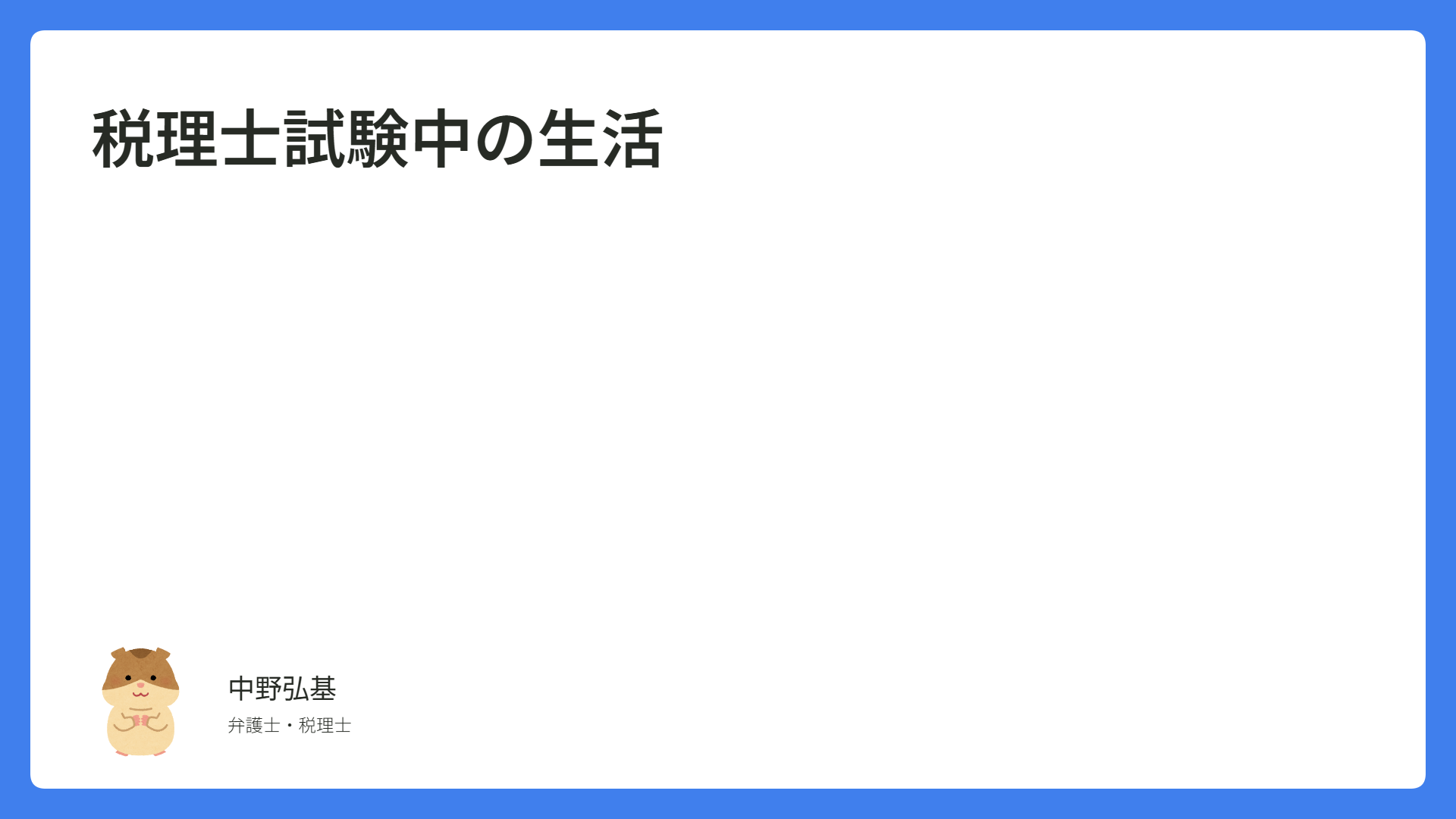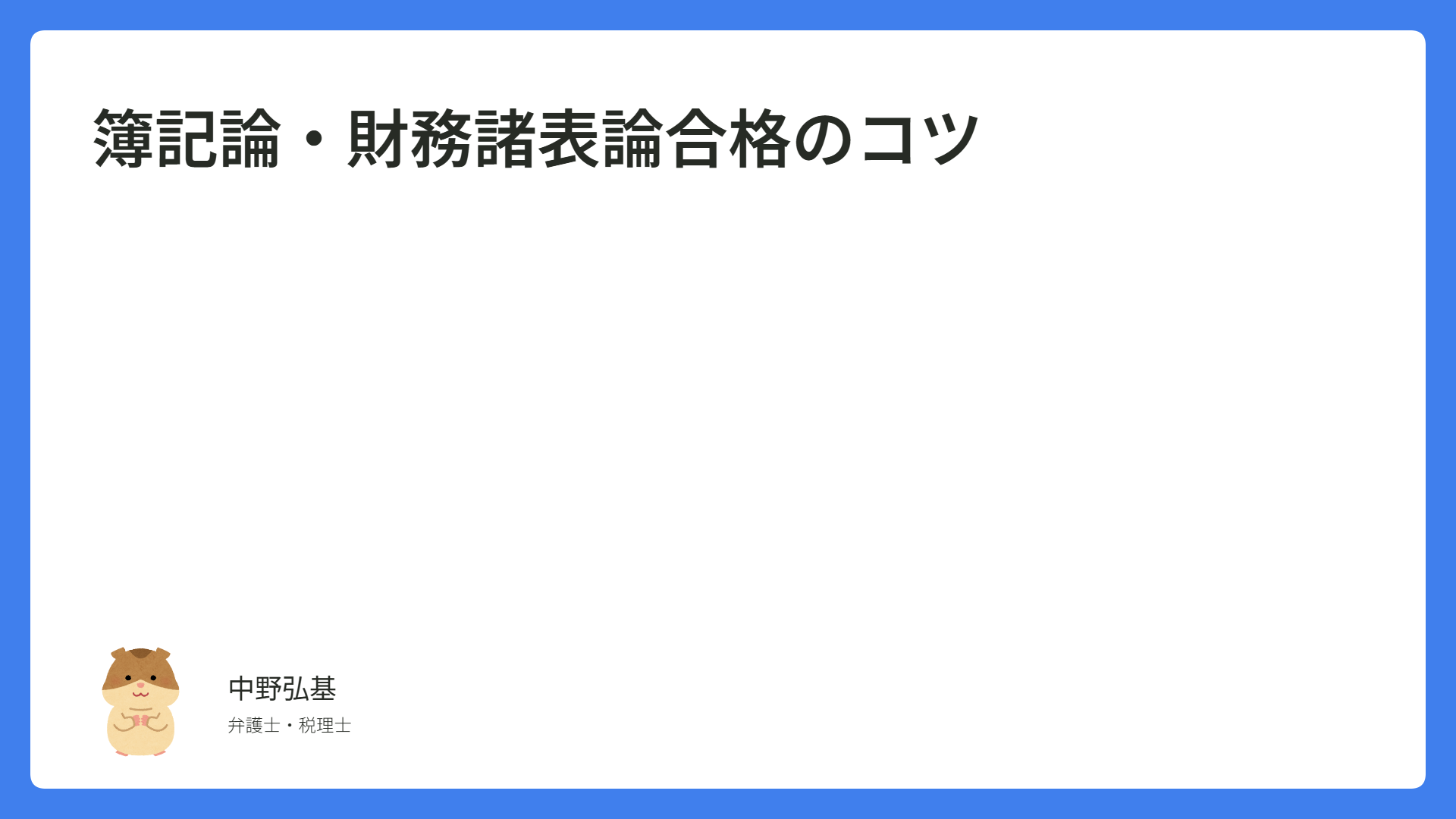相続税法合格のコツ


相続税法って難しいと聞くけど、合格のコツ教えて。

勉強時間の半分は理論に費やす!

久々に、まともなアドバイス。
弁護士は相続税法に合格しやすい
税理士事務所に勤務されている受験生は、年に何件くらい相続に関わりますか?
所長の方針によるでしょうが、年に2~3件くらいでしょうか。
法律事務所ですと、常時、仕事の何割かは相続に関係がある事件となります。
したがって、法律事務所で相続税の申告自体をするわけではありませんが、法律事務所で働いていると、常時、相続という事象に触れている状態となります。
相続という事象そのものに対して慣れがあるのが圧倒的なアドバンテージになります。
弁護士は相続税の素人である
とはいっても、弁護士は、相続税法や財産評価基本通達の内容は全く知りません。
その意味では、弁護士の資格を持っていようが、初学者と全く変わらないわけです。
ですから、皆さんと同じように、圧倒的な勉強時間を費やして、計算で1ミスもしないようにする努力の過程は同じです。
努力しなければ、弁護士だろうが何だろうが試験に落ちます。
ただ、試験会場で極限の状態におかれたとき、そして、試験委員が過去問にない新しい問題を出題してきたとき、′相続に慣れている’というアドバンテージが発揮されます。
計算は1ミスも許すな
計算問題は1ミスも許さない、というメンタルで挑んでください。もちろん実際には2~3か所は間違えると思いますし、場合によっては時間不足になると思います。
しかし、模試等の練習の段階においては、1ミスでもしたら落ちる、という強い危機感を持って勉強する必要があります。
相続税法は、他の税法に比べて、受験生のレベルが高いため、1ミスが与える影響が思った以上に大きくなります。
勉強時間の半分は理論をやる
1日の勉強時間の半分は理論に使ってください。そのぐらい理論を勉強すると、最も効率よく点数が取れます。
そして、理論はCランクまでやり切ってください。
Cランク論点が出題されなかったら、A・Bランク論点の完成度で優劣が決まります。それは他の税法と同じです。
しかし、相続税法では、もしCランクが出題されると、Cランクまで書けた人の中で合格者が決まります。
受験生のレベルが高いので、10%の合格者はCランクまで書けてしまうのです。
理論の覚え方は別記事で解説します。
まとめ
相続税法は本当にレベルが高い試験です。
法律の難解さとしては、所得税や法人税の方が難しいと思います。しかし、受験生のレベルも考慮にいれると、相続税は所得税や法人税に匹敵する難易度となります。
いろいろなバックグラウンドの受験生がいると思いますが、予備校でやるような内容を如何に完璧に仕上げるかが重要です。その意味では、弁護士だろうが、公認会計士だろうが、予備校でやるような内容を勉強しなければ、相続税法の試験には合格しません。
その意味では、焦らずに自分が積み重ねた時間を信じて、合格までひたすらに努力をしてください。