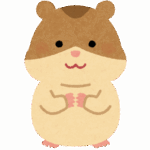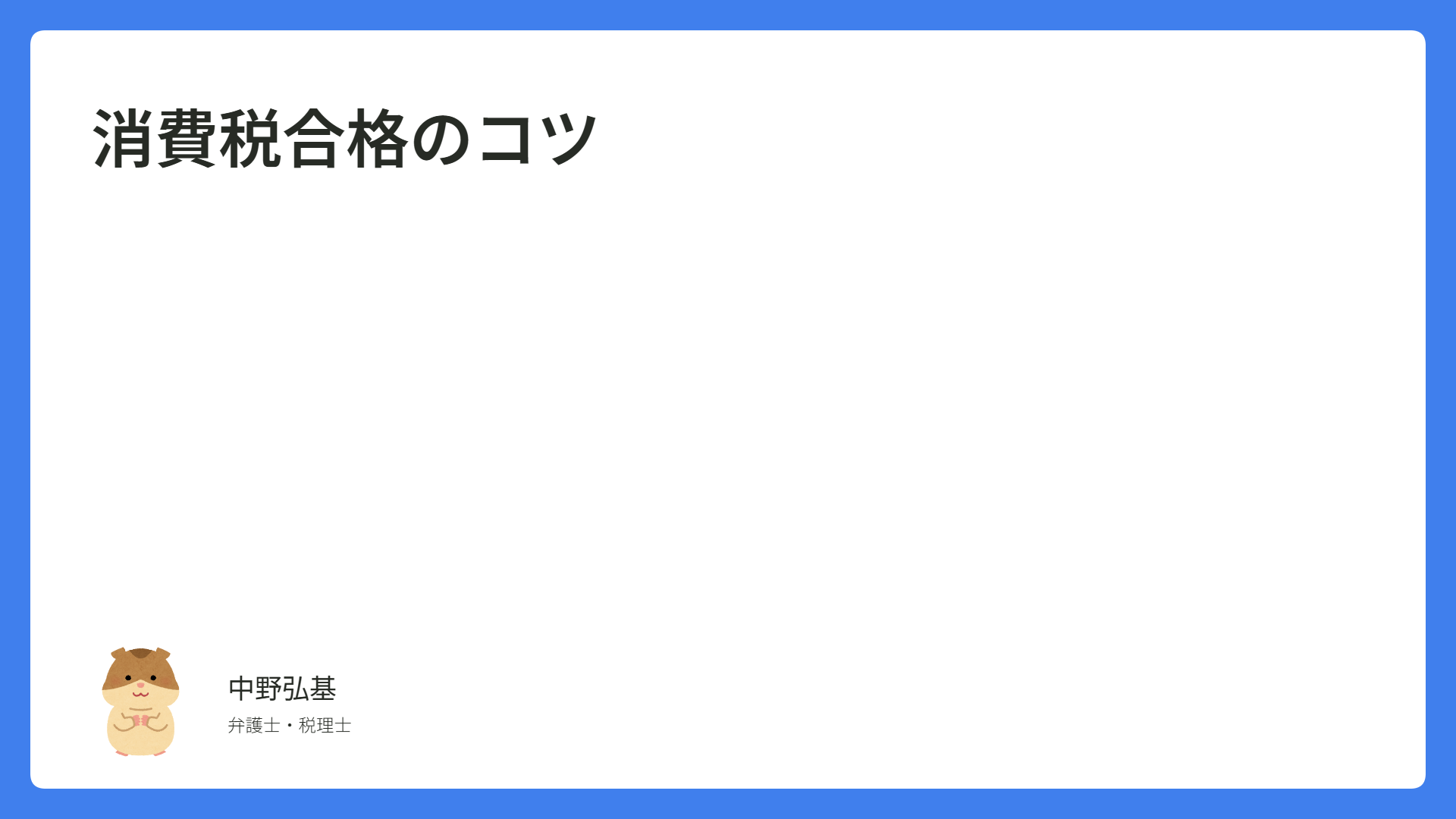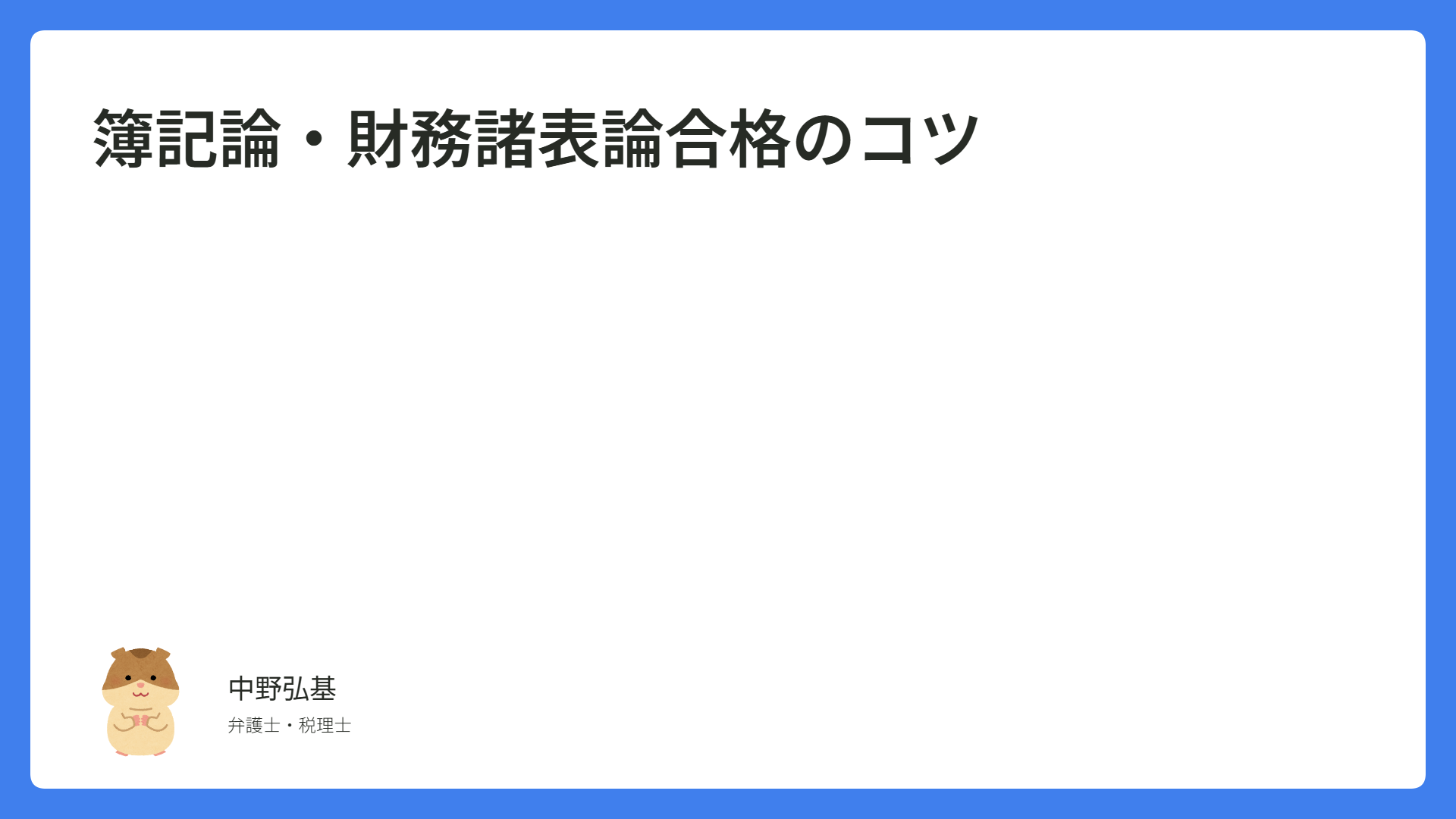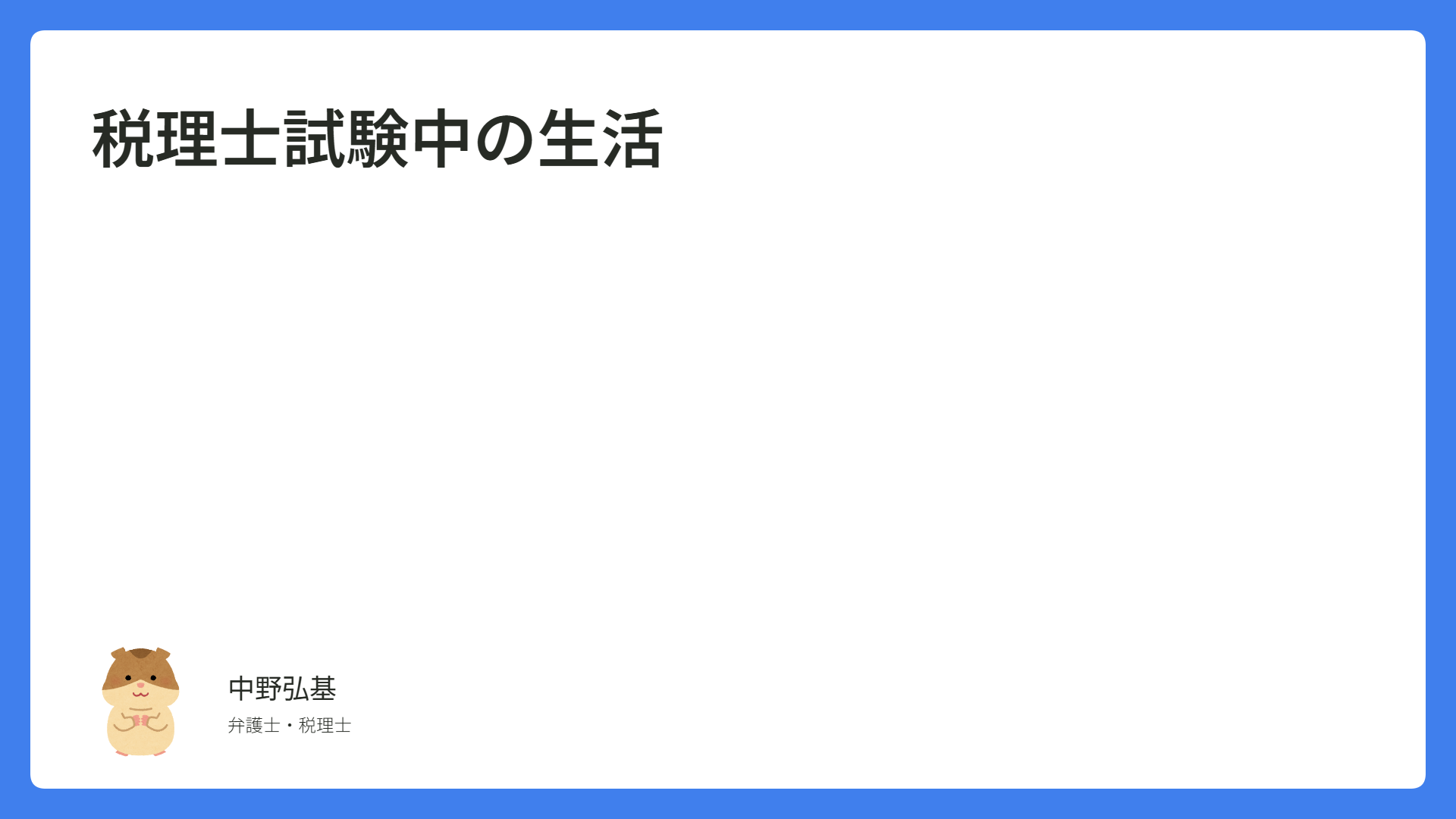理論の覚え方
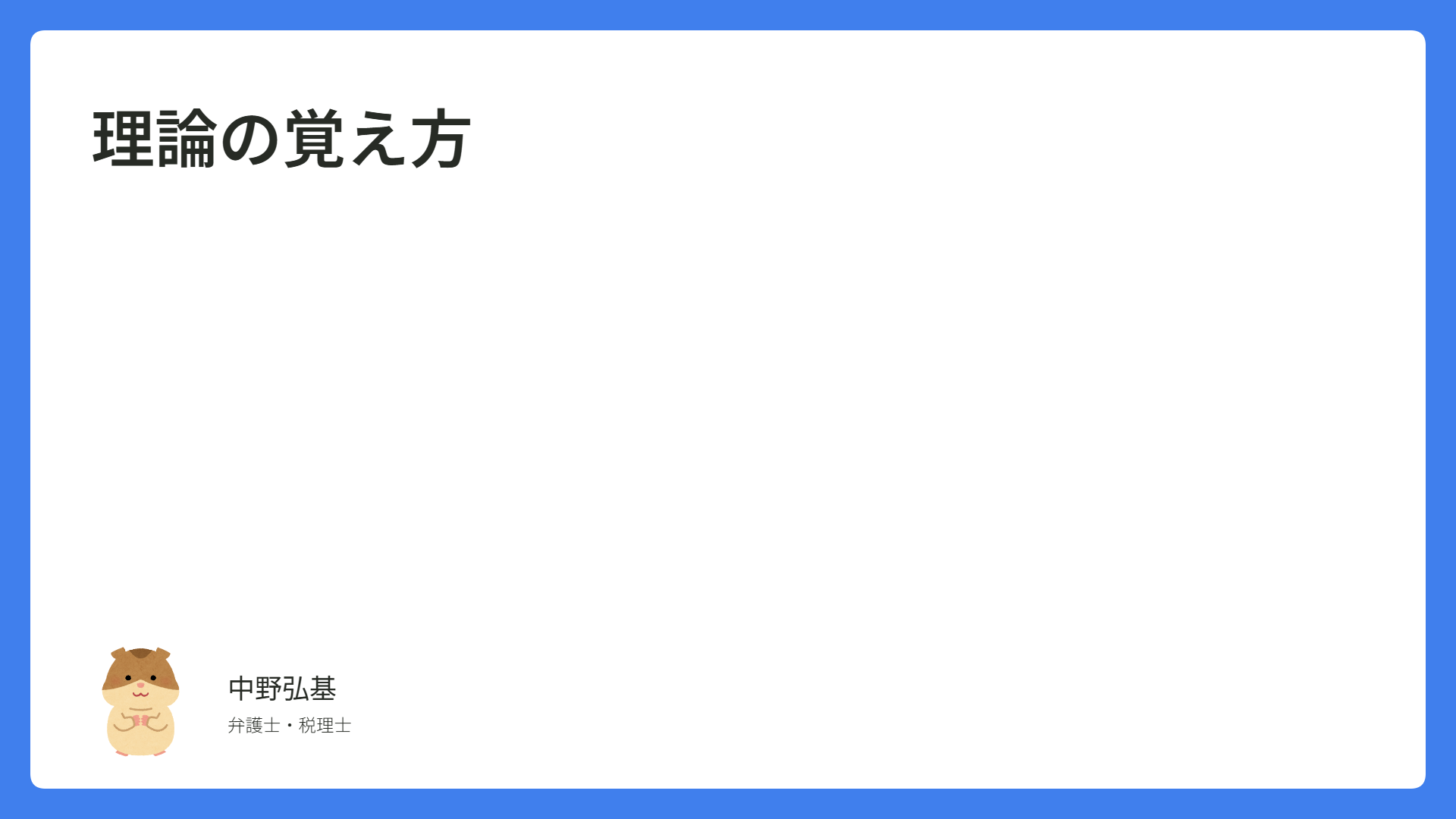

効率のいい理論の覚え方があるって聞いたけど、ほんと?

司法試験の経験を経て習得した理論の覚え方を伝授しよう

(ワクワク)
理論の覚え方は人それぞれ
皆さん、理論はどうやって覚えていますか?
テープに録音して聞く人、ブツブツと念仏を唱える人、何度も黙読する人、天性で一度見たら忘れない人、いろいろなやり方があると思います。
結果として、試験時間中に正確に条文を書き出せればいいので、それをゴールだとすれば、そこに至る過程は自由です。
そもそも税理士試験の理論って特殊です
税理士試験が初めての国家試験の人は特に違和感を感じないかもしれません。理論=条文暗記です。
しかし、もともと司法試験を先に受験した私からすると、税理士試験の理論って、ものすごく特殊です。
「理論」というか、文字通りの「条文暗記」です。
ちなみに、司法試験だと、当然論述問題の出題ですが、そもそも六法を持ち込みできますので、条文を暗記しようと意気込んでいる受験生は誰も居ません。
司法試験の場合は、条文の根底に隠れた「理論」を理解して、「理論」に基づいた条文の解釈論を展開し、具体的事案を解決する試験です。
そのため、「理論」の名目で「条文暗記」をさせられる税理士試験は戸惑いました。これ何の意味があるんだろう?と思ったものです。
いかに効率よく条文暗記するか
そうすると、大切になるのは、いかに効率よく条文暗記するか、ということです。ポイントは2つあります。
一つは、覚えては忘れるを繰り返すことです。
いったん覚えても、1か月後には忘れていると思います。でもそれでいいです。3周、4周、5周と繰り返していくと、頭に残る文章量が増えていきます。短期記憶を何度も繰り返すことで、中期記憶にぶち込んでいくイメージです。
8割くらいの正確性で思い出せるようになったら、直前対策期まではそれで完成です。一言一句は直前対策期にやります。ただし、8割というのは、小テスト前に8割の正確性ではなく、いつどこで問われても8割程度の正確性で回答できる、という状態です。したがって、小テストのカリキュラムとは別に、定期的に自分で周回して思い出し作業をする必要があります。
直前対策期において、大原であれば、試験前1か月くらいの理論周回表を渡されますから、あとはその予定に従って理論を回していけばよいです。その回していく過程で、8割の正確性から一言一句の正確性に高めていきます。
忘れる自分を許してあげましょう。
もう一つは、口で覚える、手で覚えるは幻想だということです。
どんなに周回したとしても、念仏のように唱えるだけで中身を理解していなかったら、効率が悪いです。
条文が日本語で書いてある以上、日本語の意味は理解できるはずです。
理論テキストの解説ページなんかをよく読んで、条文の趣旨、適用場面なんかを条文暗記の際にイメージできるようにしておきます。
回り道のように見えて、案外近道です。その条文で何をやりたいか理解していれば、多少、言葉を忘れたとしても作文できます。この思い出そうとしては作文する作業を繰り返して、自分の言葉から本当の条文の言葉に頭の中の情報を置き換えていきます。
まとめ
以上を踏まえて、私のやり方は、次の通りでした。
①理論テキストの条文を読む。
②解説を読んで、趣旨や適用場面、その条文でやりたいことを理解する。
③もう一度理論テキストの条文を読んで、解説のとおりになっているか検証する。検証の過程で、条文の言葉を覚えていく。
④テキストを閉じて、条文を思い出す。思い出せない箇所は自分の言葉で補う。
⑤テキストを再び開いて精度の甘いところを再び暗記する。
⑥あとは④と⑤を繰り返す。
案外、普通ですか?そうかもしれませんね。
ちなみに、司法試験だと7科目、8科目同時に受験し、その全ての科目にいっぺんに合格しないといけないですから、数千個以上の理論を覚えた上で試験会場に向かうことになります。
税理士試験は、50~80個理論を覚えればいいので、まだ簡単かな~と思います。